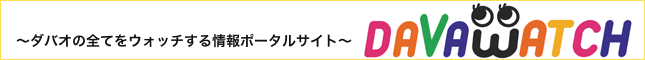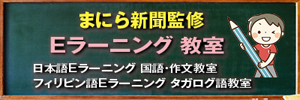台風ヨランダ(30号)
被災地へ6 日本の緊急援助隊・医療チームがレイテ州タクロバン市内で活動

台風ヨランダ(30号)が直撃したレイテ州タクロバン市。被災から10日以上たった今も市街地は破壊されたままだ。世界各国から支援の手が差し伸べられている中、日本からも支援部隊が市内に入り、活動を行っている。
19日午前11時ごろ、海沿いにある公園の入り口に日本の国旗が風にたなびいていた。公園内には「国際緊急援助隊」と書かれた複数のテントが張られており、その前に被災者が列をつくっている。テント内では、日本から来た医師や看護師らが慌ただしく動き回り、被災患者らの診察や治療に当たっていた。
この援助隊は日本の国際協力機構(JICA)に率いられた医療チーム。15日から同市で活動を展開している。医師4人、看護師7人を含む36人が毎朝8時半から診療を行っているという。
ちょうどテントを訪れていた10歳の女の子は、台風の際に足をけがし診察を受けていた。レントゲンを撮ると、足の甲に異物が入っているのが分かり、急ぎ除去手術をすることになった。援助隊の副団長、冨岡譲二医師(52)がゴム手袋をはめ、執刀にあたる。足に麻酔注射をすると、女の子は涙を流し、付き添っていた姉の胸に顔をうずめた。同行していた姉の恋人も心配そうに見つめている。富岡医師が傷口でピンセットを動かす。間もなく、足の甲からすぽりと何かが飛び出した。直径5センチほどのガラス片だった。
毎日150人ほどが訪れるという患者の半数はかぜや、栄養失調が原因の下痢などの症状を抱えているという。台風襲来の前からの慢性病に苦しむ患者も多い。病院が破壊されたため、定期受診を受けることができないのだという。数は少なくなってきたが、外傷を抱える患者の来訪も依然、続いている。
援助隊の岩上憲三団長(49)によると、被災地入りした頃と比べ、タクロバン市にも徐々に復興の兆しが見え始めているという。石けんや卵の路上販売が始まり、以前は倒木やがれきでふさがっていた路上も少しずつ片付けられている。市内をトライシクル(サイドカー付きオートバイ)で移動する際、運転手が記者に「何日か経てばタクロバンは必ず復活する」と力強く話した言葉が心に残った。
しかし一方で、被災者の多くは仕事を失い、日々の生活を支援物資に頼り切っている現状がある。食料などの物資が足りないため、セブ市や首都圏に避難する被災者も後を絶たない。やがて、差し伸べられた支援の手も少なくなって行くだろう中で、いかに地元経済を立て直していくのか。
岩上団長は「仙台を思い出す」と遠くを見るような眼差しになった。2011年3月の東日本大震災の際、仙台に入って支援活動を行った団長。タクロバン市に向かう途中で見かけた、木が倒され、家々が倒壊している同州パロ町の光景が、大地震で被災した仙台の街と重なって見えたという。
東北大震災を体験した日本人だからこそ、台風ヨランダの被災地の復興に、何らかの形で協力することができるのではないだろうか。「我々が経験した2年8カ月前と同じ光景がまさに比の被災地に広がっている」と冨岡医師は静かに語り、「震災の際、我々は世界各国から多くの支援を受けた。今度はその恩を返す時だ」と言葉をつないだ。
20日午前5時。まだ暗いタクロバン空港には、輸送機の順番を待つ数多くの人たちであふれていた。彼らが笑顔で再び故郷へ戻って来たとき、これまで1週間近くにわたり、たどった被災地をもう一度訪れてみたい。そう感じながら、記者はマニラ行きの輸送機に飛び乗った。バスで2日かけてたどった道のりを、国軍機は2時間もかからずに通り過ぎて行った。(加藤昌平、終わり)