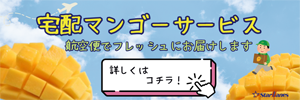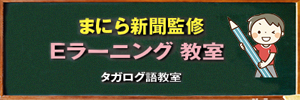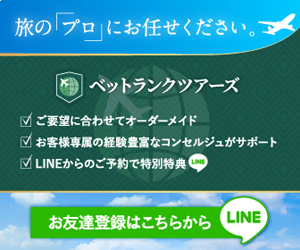ミンダナオ島の電気の通わない僻地(へきち)に、今も残留日本人の子孫たちがひっそり暮らしている――。ダバオ市から南に車で5時間、ミンダナオ島最南端・西ダバオ州ホセアバドサントス町。ここで9月中旬、残留日本人二世の国籍回復支援を行うNPO法人「フィリピン日系人リーガルサポートセンター」(PNLSC)が、フィリピン日系人会、比NGO「リッターオブライト」、ホセアバドサントス町の協力の下、簡易太陽光装置を製作・配布するワークショップを行った。それと同時に行なわれたヒアリングで見えてきたのは、日本人移民の子孫が直面してきた二重の差別と、貧困の連鎖だった。(竹下友章)
今回ワークショップの場に選ばれたのは、同町のバランガイ(最小行政区)メイビオ。ここには、戦前の移住者・羽渕清五郎の末裔(まつえい)とみられる「ハブチ」の姓を持った人々が多く住む。その中の集落の一つ「マブハイ」の住民は父系・母系含め約7割が日系人と推定される。
清五郎は多くの日本人開拓者と同様、先住民(マノボ族)との女性と結婚し、土地を取得・開拓。豊かな暮らしを手に入れ、12人の子宝にも恵まれた。しかし、大戦の最中に比米軍により連行され、処刑された。
少数民族であること、そして戦後深い恨みの対象となった日本人の子孫であること。この二つの被差別性を持つ人々が支え合うため同族同士で身を寄せ合った結果、こうした日系人マノボ族共同体が形成されたと考えられる。
▽買い叩かれる労働
マブハイ集落を川に沿って奥に進み、川を横断した先に住むジョセフ・クリストバルさん(38)は、清五郎の娘の一人と比人の間に生まれたという、母系の日系3世だ。ジョセフさんをはじめ、集落の住民は竹で編んだ伝統の「バハイ・クボ」型の住居に住み、水浴び、洗たくは近くの川で行うという素朴な暮らしを営む。
4人の子どもを養うジョセフさん。生業は、木登り1回当たり5ペソのココナツ取り、1日150ペソの山の下草刈り、1000個あたり300ペソのココナツ皮剥ぎなどだ。ダバオ地域の農業最低賃金は1日457ペソ。現代の商品・貨幣経済の中で、マノボ伝統の技は最賃を遥かに下回る単純労働として買い叩かれている。
かれらの生活の課題は何か。まず、電気がない。日が落ちると工芸などの内職や、子どもたちの勉強ができなくなる。わずかに充電式の懐中電灯を持っていても、充電するときは山を下り、電気を引いている家に行って頼まなければならない。飲料水アクセスも制限されている。山を下り開けた場所に行けば井戸があるが、そこに行くには渡河しなければならず、増水時はそれができない。増水時は渡河が危険なため、雨が降るたび子どもたちは通学を諦めなければならない――。
こうした生活水準の低さは、子ども世代から十分な教育環境を奪い、次の世代の社会的地位向上を妨げることは明らかだ。この構造は、親の世代が貧困から抜け出せなかった理由でもあるだろう。
同集落に住む、同じく清五郎の孫に当たるカウリノさん(65)は残留日本人二世の母・コウノについてこう回顧した。「母は日本人の血を引いていることで、いつ襲われるかと恐れていた。戦後はハブチの姓を隠し、フィリピン姓のみ名乗っていた」「でも母は自分のきょうだいたちと同様に、日本人として認められたがっていた。だが、(国籍回復申請のための)書類をそろえる資金がなかった」。
「母は、本当に生活が苦しいとき、『私たちには日本にハブチ家の親戚がいるから大丈夫だ』と励ましてくれた」というカウリノさん。貧苦と迫害を耐え抜く心の支えにしていた、父の祖国とのつながり。その願いは果たされぬまま、母コウノは20年前に亡くなった。
▽取り戻したいのは「誇り」
「ただモノをもらうのでなく、自分たちで作ったという経験が大切。それによって、誇りを取り戻してほしい」というPNLSCの猪俣典弘代表。ユネスコ公認NGOリッターオブライトの協力の下、太陽光発電の照明を、各世帯の父親らが自らの手で組み立てるワークショップにデザインした。日系人の多い5集落を対象としたが、配布する対象は日系人・非日系人で区別しなかった。「光の当たらない存在だった日系人が、地域を照らす存在となることを支援したい」(同代表)との思いからだ。
ワークショップ当日、会場となるバランガイ・メイビオのバスケットコートでは、準備前から話を聞きつけた住民らが会場に集まり、既にお祭りの様相。長蛇の列には、山を3時間かけて下ってきた人たちもいた。設置された作業台で組み立てをする各世帯の父親たち。その中には、真剣な表情で配線をつなぐジョセフさんの姿もあった。今回のワークショップで住民が組み立てたものも含め、約160世帯に太陽光装置が配布された。
太陽光照明を持ち帰ったジョセフさん。いつもなら暗闇となる午後6時ごろ、自分で作った照明で屋内を照らし、目を輝かせて教科書をめくる子どもたちを見守った。
「このような集落がまだあることを実際に目にして、私自身も驚いた。さまざまな要因があるが、現在の貧困は、戦争での喪失・戦後の迫害と深く結びついており、戦後はまだ終わっていないのだと痛感した」。ワークショップ日程終了後、こう振り返った猪俣体表。「今回のワークショップを通じ飲料水へのアクセスなど他の課題も見つかった。無国籍の残留日本人二世の国籍回復と並行して、日系人社会の側面支援も引き続き行っていきたい」と意気込みを語った。(続く)


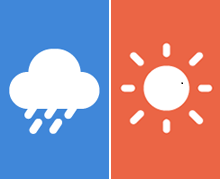


 English
English