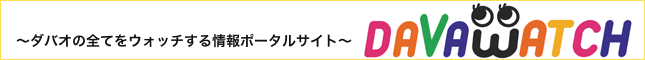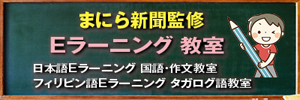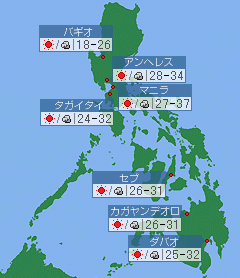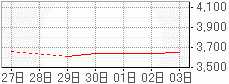連載「台風被災1年」(上)
被災地では、心的外傷によるストレス障害を発症してる被災者が多くいる

ビサヤ地方を中心に壊滅的な被害をもたらした超特大台風ヨランダが上陸してから1年が経過した。猛烈な暴風雨と高波で破壊された町並みには活気が戻りつつある。しかし、愛する家族、住宅、仕事を一瞬のうちに失い、精神を病んだり、貧困の淵から立ち上がれないまま苦しんでいる被災者も多い。
フィリピン政府は復興事業の成果を強調する。死臭が漂い、がれきであふれた「破壊の風景」は確かに一変し、復興の兆しが見え始めている。「苦悩と希望」の交錯する被災地を歩き、奮闘している被災者の声に耳を傾けた。(鈴木貫太郎)
「お金はいらない。娘に心理カウンセラーを紹介してくれないか」。そう訴えるセルヒオ・ベンドイさん(52)の目は赤く充血し、涙があふれ出ていた。
被災地のビサヤ地方レイテ州パロ町には、愛する家族を救えなかったという「非合理な罪悪感」にさいなまされ、心的外傷からストレス障害を発症する被災者が多くいる。同町サンフアキンに住むセルヒオ・ベンドイさんもその典型症例だった。
27年連れ添った妻クリスさん(52)を含む31人もの親族を一挙に失うという大変な悲劇に見舞われた。娘3人のうち、次女ニッキーさん(21)とジョイジョイさん(16) は高潮にのまれ、帰らぬ人に。大家族の中で生き残ったのは長男ウィリアムさん(27)と長女ジェニサさん(23)と自分の3人だけだった。
元警官のセルヒオさんは台風襲来時には首都圏に滞在しており、すぐ避難するよう電話で妻を必死に説得したが「台風が来ても大丈夫」と聞き入れなかったという。
セルヒオさんは「妻や娘のことがどうしても忘れられない。夜も眠れない」と心の内を吐露、顔を真っ赤にして大粒の涙を流し、号泣するばかりだ。次女ジョイジョイさんの写真を見つめながら「これが犯罪だったら、俺が犯人に仕返ししてやるのに」とおえつを漏らす。
長女ジェニサさんの症状は少し違う。自宅に高潮が押し寄せ、屋根の上に避難しようとした時、高波に飲まれ、抱いていた1歳のめいを手放してしまった。家にいた母や妹はがれきの中から遺体で見つかった。めいの遺体は1年たっても発見できていない。
ジェニサさんは「神様に『私は死んでもいいので母や妹を助けてください』と祈りました。でも、私だけ生き残ってしまったんです」と今でも自分を責め、大きく肩を落とす。
被災後、セルヒオさんは眠れなくなり、悲しみを紛らわすために酒を暴飲するようになった。笑顔で話していたかと思うと突然、号泣し、情緒不安定なセルヒオさん。またジェニサさんはインタビューの間、「感情を外に出したくありません」と無表情のまま。しかし、父が涙を流すたびに立ち上がって席を外した。数分後に戻ってくると、必ず目尻に涙が残っていた。取材しながらどう対応していいか分からなくなる時もあった。
2011年3月に発生した東日本大震災の被災地で、被災住民へのメンタルヘルス面のケアやネットワーク作りをしている福島県立医科大学医学部の前田正治教授(54)は、「ベンドイさん一家には、災害で生き残った人が抱えてしまう『生存罪責感情』がみられる」と指摘した。
「生存罪責感情」とは、ユダヤ人大量虐殺で知られるホロコースト生存者への臨床研究を通じて、1960年代に注目され始めた精神症状のひとつだ。
冷静になって考えると仕方のない状況であったとしても、「生き残った自分」を責めてしまう非合理な罪悪感から逃れられない。国籍にかかわらず災害を経験した被災者は、この感情を抱えやすいという。ベンドイさん一家の暴飲習慣や睡眠障害などは、心的外傷を受けたことによるストレス障害の典型的症状という。
前田教授は「台風ヨランダ被災地でも心のケアは行わなければならない」と強調した。教授は「ソーシャルワーカーが被災者宅を訪問するなど、地域で孤立させないことが重要です」と話した。(つづく)