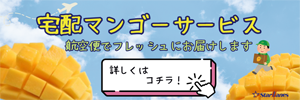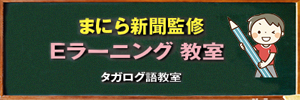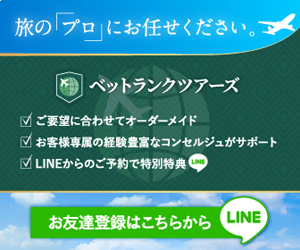ダバオ市のCAPオーディトリウムで23日、国際交流基金マニラ日本文化センターが主催する日比共同音楽公演「Ikusamonogatari II - Stories of Battle in Gaza(戦物語II―ガザの戦いの物語)」が上演された。会場には観客約50人が訪れ、日本の伝統音楽と語りで紡がれる「ガザの物語」に静かに聴き入った。
公演は古典『平家物語』や壇ノ浦の戦いの語りに着想を得た作品で、戦火の中を生きる人々の勇気、悲しみ、そして抵抗の姿を日本の伝統楽器・琵琶と箏の音色にのせて表現した。日本の古典的な「戦物語」と現代の「戦争の現実」を重ね合わせ、人間の普遍的な感情―勇気、悲嘆、無常―を描き出した。
琵琶奏者は、世界で活躍する筑前琵琶の語り手で女優の横田桂子氏。力強くも繊細な声と音の響きで『平家物語』の一節を語り会場を圧倒した。箏を担当したのは今年の外務大臣表彰受賞者に選出された社会学者・永井博子氏(アテネオ・デ・マニラ大学教員)。柔らかで且つ緊張感のある音色で情景を支え、悲しみと絶望が交錯する音の世界を生み出した。
さらに、国内最高峰の文学賞であるパランカ賞を10回にわたり受賞している劇作家で俳優のロディ・ヴェラ氏と、女優のラム・ボテロ氏が英語による語りを担当。緊迫感のある声で、爆撃の中で家族を失う登場人物たちの苦悩を表現。箏・琵琶・語りが交差し戦場の息遣いが伝わるような臨場感を生んだ。
「ガザは死体でいっぱい」「兄さんがいない」といった言葉が、琵琶と箏の響きとともに繰り返されると、劇場が深い静寂と衝撃で包まれた。すべての語りには日本語と英語の字幕がつき、観客はその意味をじっくりと味わいながら耳を傾けた。
観客の一人は、「ガザに行ったことも日本の伝統音楽を聴いたこともなかったが、音が立体的に情景を描き出し、登場人物の悲しみが目に浮かんだ」と感想を語った。演奏を終えた横田氏は「平家物語の盛者必衰というテーマが現代のガザの現実と重なる部分がある。文化も時代も異なるが人間の苦悩には共通する普遍性がある」と語った。
永井氏は、「他の楽器にできるなら伝統楽器にもできる。伝統楽器を通して、現代社会に問いを投げかけることで普遍性を浮かび上がらせられる」と話した。ラム・ボテロ氏は、「国や宗教の話ではなく、『人間の物語』としてガザを語ることが重要。アートは現実の鏡ではなく記憶を刻む手段でもある」とコメントした。(鴨志田唯=ダバオッチインターン、ダバオ市)





 English
English