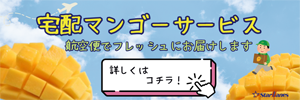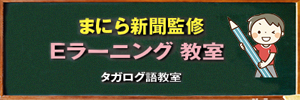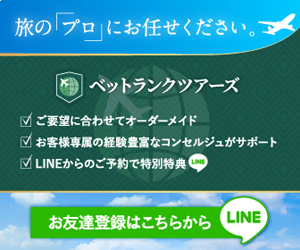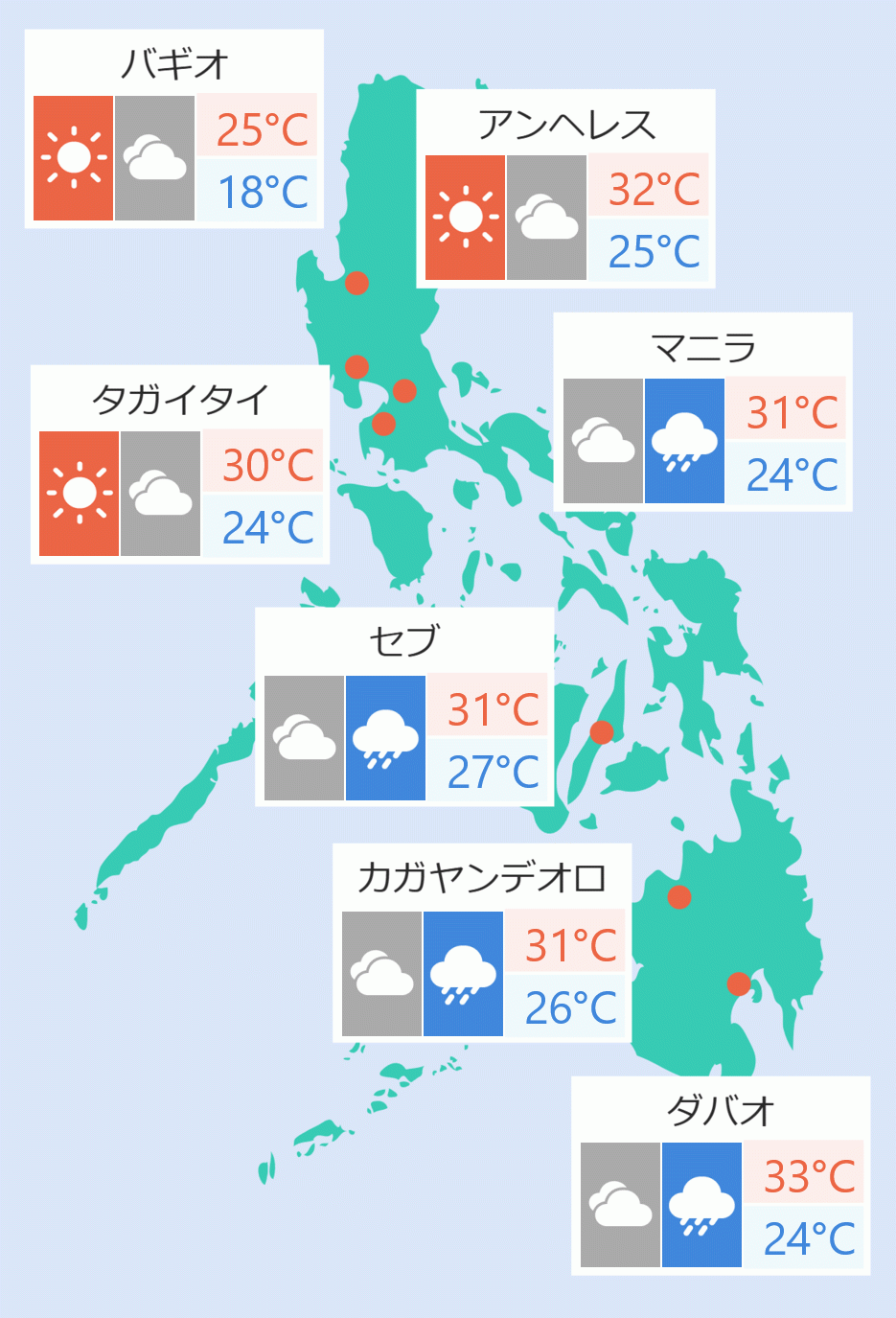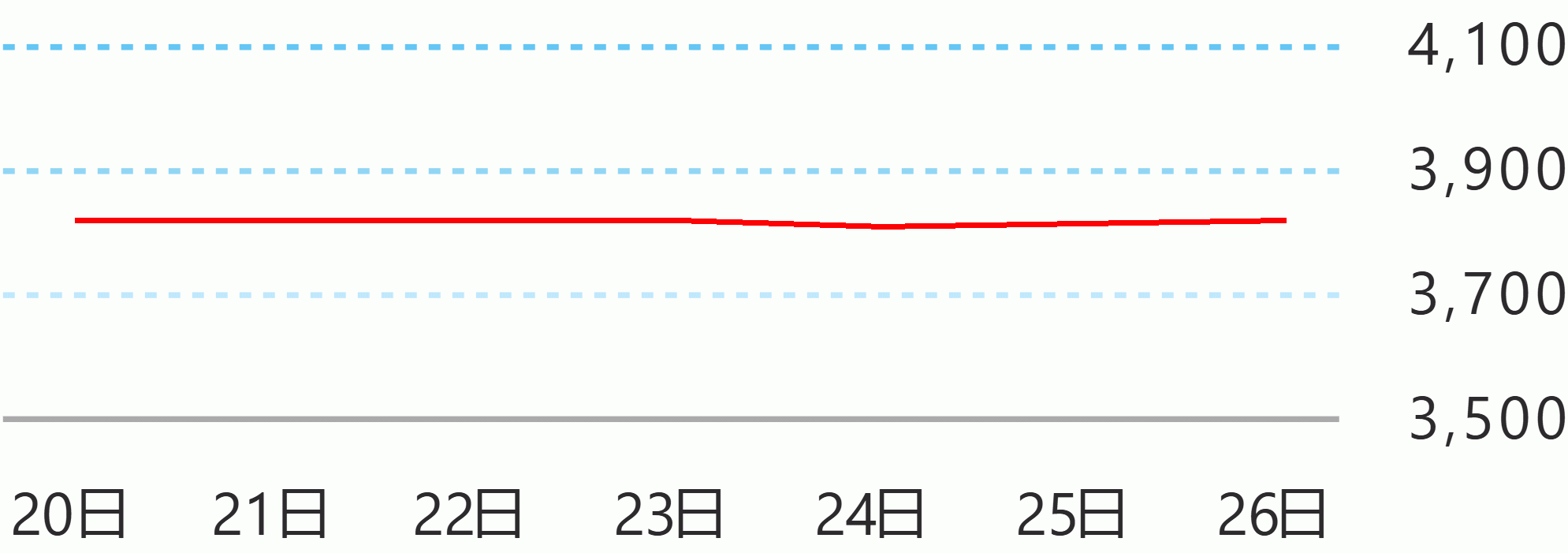まにら新聞記者が、大阪市で開催されていた大阪・関西万博に足を運び、東南アジア地域各国の展示を鑑賞した。回想連載最終回では、東ティモールパビリオンを振り返り、東南アジア諸国の展示を総括する。昨日、晴れて東南アジア諸国連合(アセアン)の一員となった同国は、コモンズ―Bに出展。「若き国が語る自然と豊かさの物語」をテーマに、観光地や農業、天然資源を紹介した。
東ティモールの展示は館内2か所に設置されていた。4カ国の展示が円形に並ぶ場内中央のエリアでは、民族衣装や民芸品を展示。銀製の頭飾りやブレスレットのほか、ビーズネックレスの「モルテン」など、沢山の装飾品が並ぶ。鮮やかな織物の文様や、魚や花が描かれた壺のデザインに、島国の風土が感じられた。なお、大半が英文だが、展示物の説明が丁寧に添えられていた。
持続可能な開発に関する展示では、海洋生態系に焦点を置いた取り組みを紹介。東ティモールは、海洋生物多様性が極めて豊かな、「コーラルトライアングル」の内側に位置している。地域発展の土台として、海洋生態系を積極的に保護し、環境にやさしい国家開発に取り組んでいるとのこと。
壁際に位置する主要展示エリアは、地域信仰に根差した高床式の小屋の模型が目印。鉱物の標本や、採掘候補地の写真、石油や鉱物資源の採掘活動候補地の地図など、資源関連産業の展示が充実していた。写真は風景に限らず、大統領の写真や、民族衣装を着た人々の写真集など様々で、人々と生活環境の繋がりが感じられる構成だった。織物やコーヒー豆の展示も種類が多かった。
東ティモールの展示は、小規模ながら展示形態が多様で、同国について多角的に学べる仕組みになっていた。また、展示エリア前に日本人スタッフが立ち、「インドネシアから独立した国」という言葉と共に、積極的に来場者を呼び込む姿も印象的だった。
▽各国社会と展示手法
大阪万博での東南アジア10カ国の展示について、展示手法と各国の社会背景の関係性に着目したい。デジタル技術を用いた展示手法は、シンガポールなど経済的に豊かな国ほど多い傾向があった。数々の先進的な技術は、ビジネス面での技術力のアピールに貢献した一方、文化的な豊かさが伝わりづらい無機質な側面も生じていた。
一方で、手工芸や民芸品を用いたアナログな展示は、社会と人々の関係性の提示に優れていた。展示部門で表彰されたカンボジアとベトナムは、統一された館内の色彩や照明が、豊富な展示物の個性を引き出していた。同じく、展示部門で表彰されたインドネシアとフィリピンは、展示に大きな映像を用いつつ、織物の模様や自然を映像内で積極的に使用。アナログとデジタルのバランスを工夫した展示構成だった。
各パビリオンの設計方針と用いる手法は、来場者を楽しませて文化学習を促す、最も表層的な目的だけではなく、地域ごとの細かな特色が表れている。歴史、注力産業、未来の成長構想など、各国のあらゆる社会的背景が、パビリオンの特色を戦略的に、時に無意識的に形成していた。
いつかミャンマーが万博に参加し、アセアン11か国がより多彩な社会を提示する日まで、私の東南アジアの解像度はどのくらい上がるだろうか。(宇井日菜)





 English
English