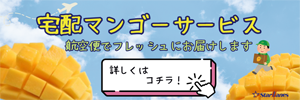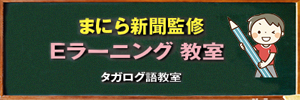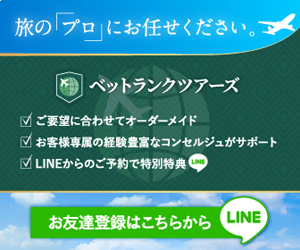国際交流基金マニラ日本文化センター(JFM)は13~17日の日程で、全国の中等教育機関において日本語教育に携わるフィリピン人教員の一部を対象に、日本をより身近に体験し、理解してもらうための「フォローアップ・セッション」を実施した。JFMでは2009年以降、ジュニアハイ(日本の中学1年~高校1年に相当)の日本語教員養成プログラムを開講。夏休み期間中に3週間の短期集中「インテンシブ・コース」を終えた教員らは、新学期から隔週土曜日に遠隔授業を受け、レベルアップを図りつつ、同時に所属校で日本語授業を受け持っていく。
2023年までは一連の研修期間が2年間で、新規教員の募集は隔年だったが、24年以降は期間を1年間に短縮し、年一回の教員募集へと変わった。また、1期~5期までは本プログラムを日本で実施してきたが、6期(22年度)以降は比国内での実施に変わり、昨年に続いて今年で2回目だという。一年間のプログラムの集大成に当たる今研修への参加者は24年度募集教員(第7期)のうち、21人(女性20人、男性1人)が参加。教育省の資金協力を得て、首都圏マカティ市のホテル「セント・ジャイルズ」にて5日間泊まり込み、参加者にとっては初対面の機会ともなった。
▽比で深める日本理解
初日は教育省プログラム統括責任者のエベネザール・ベロイ氏、JFMの鈴木勉所長らの挨拶で幕が開き、参加者同士のアイスブレイクや自己紹介、JFMの専門家による教務内容へと移っていった。二日目からは日本文化体験も始まり、マカティ市内にあるマニラ日本人会の事務所内の茶室にて、茶道裏千家淡交会マニラ協会による茶道の作法を順番に目にし、茶と和菓子をたしなんだ。英語が流暢な講師からは「足を崩して座って構いませんよ」との指示があるも、畳の上でなれない正座に挑戦し、足がしびれた参加者もいた。質疑応答ではすり足の歩数や生活の中での茶道の位置づけを問うなど、参加者の知的好奇心の高まりが感じられた。
三日目には午前中に首都圏タギッグ市のマニラ日本人学校(MJS)を訪問。昨年に続いて二度目となる訪問で、片山公善校長、溝江繁教頭の案内で校内を回った。小学部2年と、中学部2年の教室でそれぞれ行われたフィリピン人教員との交流プログラムでは、比側からは子どもの歌や簡単なタガログ語、サリサリストアでの買い物の仕方などが、日本語で実演された。中学部2年生も、日本のゲームや日光東照宮、厳島神社、グミッツェルなどを紹介。比人教員から「日本のお勧めのお土産」について聞かれた生徒たちは、広島名物のもみじ饅頭(まんじゅう)を挙げていた。小学部では英語を理解する生徒も多く、個人的に比教員と意思疎通を図る生徒もいて、すぐに打ち解けていた様子だった。片山校長によると、MJSの全校生徒数は480人、うち中学部が100人。教員は日本人が35人、比人の英会話教員が6人いるとのこと。ネグロス島から参加した女性教員は、交流後に「とても可愛かったし、みんな元気がよくて疲れるほど」と感慨深げだった。比の学校と比較してもらうと「フィリピンの学校はもっと騒々しく、生徒たちもやんちゃで困る」と笑った。
その後も、JFM関係者による水引体験では紐3本を合わせたあわじ結び、梅結びを苦労しながら覚えていた。いけばなインターナショナル・マニラ支部108による華道体験では、役枝3本による基本形を学んだ。教育省の参加者も含め、一人一人の作品を同支部の特別講師であるエバンジェリン・チェン氏が丁寧に手を加え、完成品に仕上げていった。四日目にはラグナ州サンタロサ市にあるトヨタ・モーター・フィリピン(TMP)を訪問。教員ら一行は、現在ヴィオスとイノーバ、タマラウの生産に注力する工場の一部を約1時間かけて見学した。TMPでは正規・派遣合わせて2129人が働いており、平均年齢は33歳だという。一行は敷地や工場の規模の大きさに目を見張っていた。巨大なプレス機や動力を使わずにバンパーを運ぶ「からくり」、所々で導入されたロボットなどを実際に目にし、人材育成や職場環境の改善、製品にかけるTMPの思いを聞き、いずれもが感化された様子だった。
JFMにて2023年から日本語教育専門家を務め、10月末に帰国する予定の伊藤亜紀さんは、中心になって研修準備を進めてきた一人だ。担当はルソン島内のジュニアハイだが、先月末にはミンダナオ地方ダバオ市でも、自身が推進する「拠点校構想」具体化の第一歩として、近郊などから日本語教師を集めての地方研修を実施した。研修最終日の閉会式で伊藤さんは、「全員が研修を楽しみながら受けてくれて嬉しい」と喜びを表しつつ、「互いにこうして会うのは初めてだったけれど、ずっと一緒にいたような思いがした」と語った。その後、言葉に詰まった伊藤さんの頬を涙が伝い、もらい泣きする教員も多かった。「インテンシブが最初のステップ。これが次のステップで、みなさんにはまだ3つ目のステップが待っている」と日本語習得には終わりがないことを含ませ、教員たちのやる気を鼓舞した。
▽緊張で迎えた研修から
カビテ州で生まれ、小学2年以来首都圏モンテンルパ市で育ったシャハラシャマレシア・ハパ先生(30)は、同じく首都圏のラスピニャス市にあるキャプテン・アルバート・アギラ―国立高校で、3年間にわたって日本語を教えてきた。それ以前にも同校には日本語教員はいたが、日本へ行ってしまい、授業存続の危機におちいった。そのため、JFMの2024年度研修受講以前から、タガログ語教員のシャハラ先生が独学で日本語授業を受け持っていたという。現在JFMでは25年度研修(第8期)で同校にもう一人の教員を養成中だ。この他にもJFMからは比人教員の日本語授業を補佐する「日本語パートナーズ」が近隣校との兼任で派遣されている。今回の研修を終えたシャハラ先生は「私自身そこまで日本語が話せないし、みんなとの対面は初めてで、特に日本語の専門家と会うことにすごく緊張があった」と明かした。そのうえで「日が経つにつれて、だんだん居心地が良くなっていくのを感じた。今日、五日間の研修をやり遂げた自分をほめてあげたい」。また、比国内でのフォローアップ研修実施に対しては、「国内ではあっても、日本にいるみたいだった」と話し、同研修を支えた関係者への感謝を口にしていた。(岡田薫)





 English
English