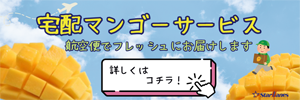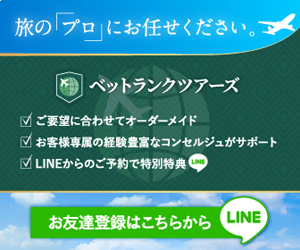まにら新聞記者が、大阪市で開催されていた大阪・関西万博に足を運び、東南アジア地域各国の展示を鑑賞した。回想連載第4回では、シンガポールパビリオンを振り返る。「ゆめ・つなぐ・みらい」というコンセプトのもと、シンガポールが夢を現実に昇華する過程を表現。テクノロジーを最大限活用した、モダンで洗練された展示が来場者を魅了した。
同館は、「ドリーム・スフィア」と呼ばれる赤い球体の建築を、下から上へ鑑賞する構造。球体を覆う赤いうろこには、数種類の細かな凹凸で模様が施されている。シンプルな装飾と、「SG(シンガポールの略称)」と書かれたロゴは、無駄を極限まで削いだ現代的な感性をまとっていた。
館内には、同国出身のアーティストによるインスタレーション作品が3章構成で並ぶ。第1章は、多くの夢が生まれる場所としてのシンガポールを表現する導入部。大きなスクリーンと、植物や動物の白い切り絵が来場者を迎え、夢と自然共生のコンセプトを提示していた。
切り絵の鳥に導かれるようにつながる第2章は、自然と都市の共生に関する取り組みの詳細を、インスタレーション作品とともに紹介。国内の自然観察システムや、公営住宅のテクノロジーに関する事業の説明が、白を基調とした室内に溶け込むように並んでいた。天井から垂れ込む大量の切り絵の葉が、都市と自然の融合そのものを体現していた。
第3章は、夢の共有をテーマにした空間。来場者は、「ドリーム・リポジトリ」という作品に設置された端末に夢を描きこむ。スロープを上り、ドーム状の巨大スクリーンが設置された部屋に移動すると、同国の主要民族である中華系、マレー系、インド系とみられる3人の子供たちが木を育て、自然や街が成長するアニメーションが上映される。下の階で入力された来場者の夢は、映像内の演出と共に、筆跡そのまま浮かび上がった。
▽都市国家のいち到達点
1965年の独立以降、アジア経済の中心地として急速な成長を遂げたシンガポール。すでに成熟した都市国家としての文化が、技術と創作の融合における1つの完成系として提示されていた。同時に、同国が培ってきた「魅せる」技術にも注目したい。
同館は他国の展示と比べ、多くの人々が自撮りや作品撮影にいそしんでいた。一方、来場者が都市開発や政策の説明に注目する時間は短く、あまり興味を持たれていないように感じた。展示物についても、作品の存在感に比べて政策の説明がひかえめで、展示環境が事業の詳細説明に適していない印象を持った。
しかし、作品を主体とした同館の展示設計は、SNSの普及した現代社会と、大量の来場者数に適した構成だったと考える。万博は、専門教育の場というより、各国に興味を持たせる導入としての役割が主体だ。また、大量の来場者数と回転率の都合上、どのパビリオンも短時間で来場者に要旨を伝えなければならない。
シンガポール館の展示は、自国に興味を持たせる「種まき」に優れていた。来場者が撮影した写真はSNSに投稿され、インターネット上でシンガポール館を宣伝する役割を果たす。事業の説明は全て読まれずとも、文中のキーワードや作品で伝えられた都市計画の概念が少しでも印象に残れば、万博閉幕後に来場者がシンガポールのことを思い出すきっかけとなるのだ。
鑑賞体験の宣伝と、未来への持続性も計算された同館の展示は、シンガポールだからこそ実現できるものだ。タンカーによる国際中継貿易や観光など、時代の流れを見据えた発展に注力してきた、同国の歩みと挑戦する姿勢が表れていた。(宇井日菜)




 English
English